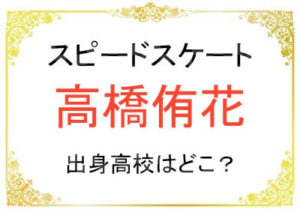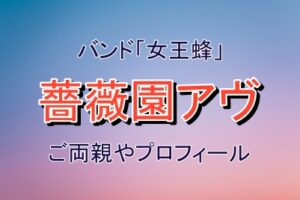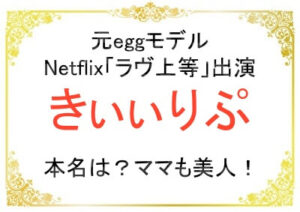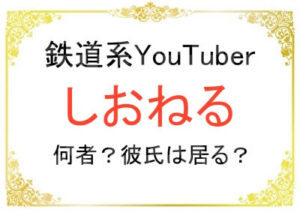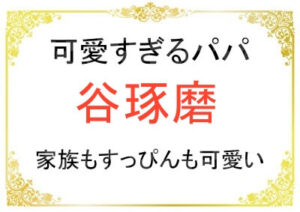職場で目上の人や部下、同僚を呼ぶときに「〇〇ちゃん」と呼んでいませんか?
親しみを込めた「ちゃん付け」ですが、最近では「ハラスメントになるのでは?」と問題視されることが増えてきました。
2025年10月には、とある会社の女性従業員に対する男性同僚からの「ちゃん付け」呼びやその他の問題行動がセクハラ認定され、慰謝料22万円の支払いを命じられています。
この記事では、「ちゃん付け」がハラスメントになり得るのか?その背景と適切な呼び方、そして職場の人間関係を円滑にするためのヒントを解説します。
【この記事で分かること】
・「ちゃん付け」がセクハラになりうる理由
・どう呼べば良いのか
今まであまり気にしたことがなかったのですが、仕事で年下の方と接する機会が増えてきたのでちょっぴりビビっております。
なお、ちゃん付け自体は問題ありませんが、言う人の人柄や関係性によって受け取り方が変わる、というのが実際のところです。
ぜひ最後までご覧ください!
「ちゃん付け」がハラスメントになる理由は?
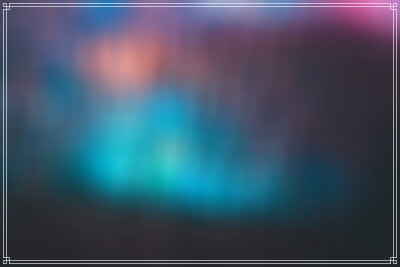
職場で親しみを込めて使われる「ちゃん付け」が、なぜハラスメント、特に「パワーハラスメント(パワハラ)」や「セクシャルハラスメント(セクハラ)」と見なされるようになってきたのでしょうか?
その理由は「相手への敬意の欠如」「上下関係の強調」そして「性別に基づく不適切な扱い」にあります。
まず、「ちゃん付け」は一般的に、年下の人や親しい間柄、あるいは幼い子どもに対して使われる表現です。
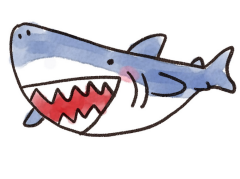
自分より小さくて可愛いものに使うイメージがあります
この呼び方を職場の同僚や部下、特に年上の人やキャリアのある人に対して使うと、相手を「自分よりも下」に見ている、あるいは「子ども扱いしている」という印象を与えてしまいます。

プライベートはともかく「職場では違う」と感じる人は多いかも

例えば、経験豊富な女性社員に対して、役職名や「さん付け」ではなく「〇〇ちゃん」と呼び続けることは、その社員の能力や貢献を認めず、見た目や性別で判断している?と受け取られかねません。
これは、職場における個人の尊厳を傷つける行為であり、パワーハラスメントと認定される可能性があります。
実際に、厚生労働省が定めるパワーハラスメントの定義には「優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」が含まれています。
不適切な「ちゃん付け」はこれに該当するリスクがあるのです。

ヤバい使ってたかも
また、特に女性社員に対してのみ「ちゃん付け」が多用されるケースでは、それが性別を理由とした差別的な扱いに繋がり、セクシャルハラスメントと見なされる可能性も出てきます。
例え悪意がない場合でも、受け取る側が「不快だ」「尊重されていない」と感じた時点で、ハラスメントとして成立してしまうのが現代の職場のルールです。
人間関係を円滑にするための「親しみ」のつもりであっても、相手に心理的な負担を与えてしまっては本末転倒ですよね。
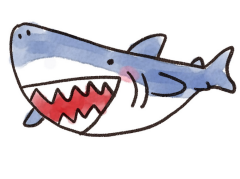
時代が変わってきていますね
職場環境の変化と多様性の尊重が進む現代において、「ちゃん付け」の使用は非常にデリケートな問題となっているのです!
「ちゃん付け」はパワハラとセクハラの境界線

「ちゃん付け」がハラスメントとなる場合、具体的に「パワハラ」と「セクハラ」のどちらに該当するのかという点は重要です。
これは、どのような状況で、誰に対して行われたかによって判断が分かれます。
パワハラ?
一般的に、上司が部下に対して「ちゃん付け」を用いる場合、それは「優越的な関係を背景とした言動」であるため、パワーハラスメントに該当する可能性があります。
例えば、課長が部下の男性社員に対して「〇〇ちゃん、これお願いね」と日常的に呼ぶ行為は、部下の立場を軽んじ、上下関係を利用した精神的な圧迫と受け取られることがあります。
この場合、性別に関わらず、上司という立場を利用して相手の尊厳を傷つけているため、パワハラと見なされるのです。
セクハラ?
一方、セクシャルハラスメントに該当するケースは、主に女性に対してのみ「ちゃん付け」が使われ、それが性的な意味合いや女性蔑視の感情と結びついている場合です。
例えば、特定の女性社員にだけ「〇〇ちゃん」と親しげに呼びかけたり、仕事内容とは関係のない部分で「可愛らしい」といったニュアンスを込めて呼びかける行為が挙げられます。
相手を性的な対象として見ている、あるいは女性であることを理由に不当に扱っていると受け取られかねません!
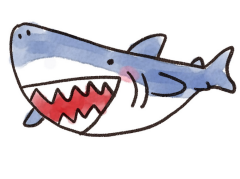
今までの「ちゃん付け」は親しみの意味もありましたが…

最近は小学校でも男女共に「さん」付けだよね
飲み会などのプライベートな場であっても、職場関係者との間であればハラスメントと見なされる可能性があるため注意が必要です。
重要なのは、行為者の意図ではなく受け取った側の「不快感」であり、「ちゃん付け」が性別を理由とした不当な扱いに繋がっていると判断されれば、それはセクハラとなり得ます。
正直、最近は「~ハラ」に敏感で不用意に発言しにくい雰囲気になってきているのは事実です。
職場での「ちゃん付け」がもたらす悪影響は?

「ちゃん付け」の使用は、単にハラスメントと見なされるリスクがあるだけでなく、職場の生産性や人間関係にも深刻な悪影響をもたらします。
一見、親しみやすい雰囲気を作っているように見えても、実は組織全体にネガティブな影響を与えている可能性があるのです。
最も大きな悪影響の一つは「コミュニケーションの停滞」です。
「ちゃん付け」で呼ばれることで、当事者は「自分は軽く見られているのではないか」と感じ、上司や先輩に対して建設的な意見や反対意見を述べることが難しくなります。
萎縮してしまい、本来発言すべき重要な情報を伝えられなかったり、自分の能力を最大限に発揮できなくなったりするのです。
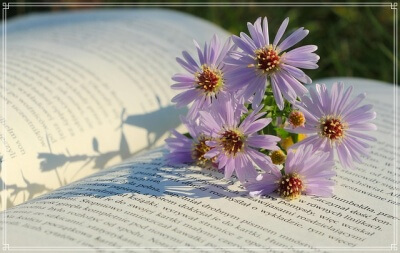
また「職場の雰囲気が悪化する」という点も無視できません。
「ちゃん付け」をされる人、しない人が混在する職場では、呼ばれる人が「特別扱いされている」「差別されている」と感じ、不公平感や嫉妬心が生まれる原因となります。
特に、年齢や入社時期が近い同僚間で、一方だけが「さん付け」で、もう一方だけが「ちゃん付け」で呼ばれている場合、呼ばれている方は「自分は一人前として扱われていない」と感じてしまうでしょう。

俺は「◯◯君」って呼ばれても違和感覚えたことなかったな。気をつけよう
さらに、ハラスメントとして訴えられた場合「企業の信用失墜」という致命的なダメージにも繋がります。
ハラスメント問題は、外部に公表されることで企業のブランドイメージを大きく損ない、優秀な人材の離職や採用活動への悪影響も引き起こします。
「たかが呼び方」と軽視されがちな「ちゃん付け」問題。
呼び方一つで、組織全体の士気、生産性、そして企業の未来にまで影響を及ぼす可能性があることを理解することが大切です。
呼び方の変化と時代の流れ

なぜ、かつて許容されていた「ちゃん付け」が、現代では問題視されるようになったのでしょうか。
これは、社会全体の「価値観の変化」と「多様性の尊重」が背景にあります。
かつての日本では、年功序列や男性優位の考え方が根強く、職場での上下関係は絶対的なものでした。
そのため、上司が部下を「ちゃん付け」で呼ぶことは、「親愛の情」を示す一種のコミュニケーションとして受け入れられる側面もありました。
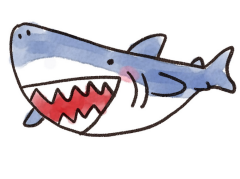
「可愛がられている」と感じる人もいますよね
しかし、現代社会では、性別、年齢、国籍、キャリアに関わらず、個々の人権と能力を尊重するという価値観が浸透しています。
特に、グローバル化が進む現代のビジネスシーンでは、欧米諸国のように役職や性別に関わらず「Mr.」や「Ms.」で呼ぶのが一般的であり、日本企業もこの国際的なスタンダードに近づきつつあります。

また、若い世代を中心に「プライベートと仕事の線引き」を重視する意識が高まっています。
仕事の場では、親しみの表現よりも、プロフェッショナルとしての「敬意」を持って接してほしいと考える人が増えているのです!
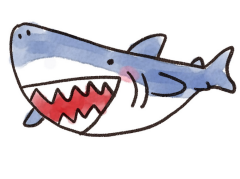
Z世代の扱いに悩む管理職は多いようです

若者からしたら線引きが甘い方が異常に感じるよ
親しみを込めたつもりでも、公の場で「ちゃん付け」をされると「TPOをわきまえていない」と感じたり「恥ずかしい」と感じたりする人もいます。
このような時代の流れを受け、多くの企業がハラスメント防止の観点から、職場での呼称を「さん付け」に統一する動きを見せています。
これは、誰もが対等な立場で意見を交わし、能力を発揮できる、よりフラットで健全な組織文化を築くための重要な一歩と言えるでしょう!
適切な職場の呼び方と円滑な人間関係

職場の人間関係を円滑にするための適切な呼び方で推奨されるのは、性別や年齢、役職に関わらず「さん付け」に統一することです。
「さん付け」は相手に対する最低限の敬意を示す、最も安全で普遍的な呼称です。
「〇〇さん」と呼ぶことで組織内の全ての人が対等な人間として尊重されているというメッセージを伝えることができ、誰に対しても失礼がなく、ハラスメントのリスクを極めて低く抑えられる点がメリットです。
また、フラットな組織文化を醸成し、役職や年齢に関わらず自由に意見を交換しやすい環境を作り出す効果もあります!
役職名での呼び方
次に推奨されるのが「役職名」を付けて呼ぶ方法です。
「〇〇部長」「〇〇課長」など、役職名で呼ぶことは、相手の職務上の責任や功績を認め敬意を示すことになります。
特に、外部の顧客や取引先との会話では、役職名を使うことがビジネスマナーとして必須とされています。
しかし、社内においては、過度に役職名にこだわることで上下関係が強調されすぎてしまい、風通しの悪い組織になるリスクもあります。
そのため、最近では「役職名+さん」で呼ぶ企業も!

例えば「〇〇部長さん」「〇〇課長さん」といった呼び方

なんとなく慣れない…
これは、役職への敬意と、個人への敬意を両立させる非常にバランスの取れた方法として注目されています。
ニックネームの使用は慎重に
「ニックネーム」や「あだ名」を使うことは非常に慎重な判断が必要です。
ニックネームを使用する場合は、必ず「本人からの許可」を得ることが大前提です。
そして、そのニックネームが、第三者から見て不快に感じられないか、公の場でも問題なく使えるかを確認する必要があります。
また、全社的に共通のルールとするのではなく、非常に親密な関係性が構築されている特定のチーム内でのみ使用を限定するのが望ましいです。
さいごに
今回は、職場で問題視されている「ちゃん付け」がハラスメントになる理由と、適切な呼び方について詳しく解説しました。
【この記事で分かること】
・安易な「ちゃん付け」はリスクが大きい
・性別や年齢、役職を問わず「さん」呼びが好ましい
「親しみを込めたつもり」の「ちゃん付け」も、受け取る側の感じ方次第でトラブルに発展するリスクがあることが分かりましたね。
ハラスメントを未然に防ぎ、誰もが気持ちよく働ける組織を作るためには全ての同僚を「さん付け」で呼ぶのが最も安全で効果的な方法です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!